2025年夏に公開される映画『近畿地方のある場所について』は、ネット発の話題作を原作としたモキュメンタリースタイルの作品。
事実と虚構が交錯するその世界観は、知っていても“怖い”と言われる独特な構造を持っています。
本記事では、小説を読んでから映画を観た場合に面白さが損なわれるのか?という疑問を軸に、作品の構造や魅力、小説と映画の違いを丁寧に整理していきます。
- 小説を読んでも映画の怖さや面白さは損なわれにくい
- モキュメンタリー形式のため、映像体験が主体
- 怖さを軽減したいなら事前の読書は有効
- 書籍版はWeb版より話が追加されている(カラオケの話など)
映画『近畿地方のある場所について』とは?

映画『近畿地方のある場所について』は、近畿地方に実在するかもしれない“とある地域”をめぐるモキュメンタリー形式のホラー作品です。
「事実」と「虚構」の境界が曖昧な構成が特徴で、演出もまるでドキュメンタリー番組を観ているかのよう。
作中では、地元住民の証言や、古い記録、地図、そして取材映像が少しずつ繋がって、不気味な全体像が浮かび上がっていきます。
映画化を手がけるのは『ノロイ』『地獄少女』『オカルトの森へようこそ』などで知られる白石晃士監督。
主演には菅野美穂さんと赤楚衛二さんが起用されており、2025年8月8日(金)に全国公開予定です。監督は「映像化という呪術を仕掛けていく」と語っており、原作の“感染的な怖さ”をどう描くのかが注目されています。
Web版と書籍版の違いについて
原作となる小説『近畿地方のある場所について』は、元々Web小説サイト「カクヨム」に投稿された作品です。
その後、KADOKAWAから書籍化された際にいくつかのエピソードが追加されており、中でも「カラオケの話」は書籍オリジナルエピソードとして読者から高く評価されています。
そのため、すでにカクヨム版を読んでいる方でも、書籍版であらためて“新たな怪異”に出会える構成になっています。
見る前に小説を読むと面白くなくなる?
結論:読んでも問題なし、むしろ効果的
この作品は、ストーリーの結末よりも「過程」「体験」「映像の異様さ」に価値がある映画です。したがって、小説を読んで物語の大筋を把握していたとしても、
- 実際の映像に映る違和感
- インタビュー音声のリアルさ
- 映像の中の異常な空気感
といった“感覚の怖さ”は十分味わえます。
特に怖がりな方には、先に内容を把握しておくことが精神的な備えにもなるので、小説を読んでおくことは有効な手段と言えるでしょう。
また、小説はオカルト雑誌のライター「背筋」が、行方不明になった友人「小沢」を探す過程で“近畿地方のある場所”にまつわる複数の怪談や記録を集める構成。
各章がSNS投稿・インタビュー・過去記事の引用で構成されており、読者自身も呪いに巻き込まれていくような構造になっています。
背筋は最後に「あなたもこの話を読んでしまったのですね。ごめんなさい」と締めくくるなど、作品そのものが呪いを媒介する仕組みになっており、映画でもそのメタ構造がどう描かれるのかが見どころです。
小説と映画、それぞれの怖さの違い
| 項目 | 小説 | 映画 |
|---|---|---|
| 怖さの種類 | 情報の積み重ねによる不気味さ | 映像・音・間による視覚的・聴覚的な怖さ |
| 得られる情報 | 登場人物の背景や詳細、資料的視点 | 実際に”体験してしまう”臨場感 |
| 向いている人 | 理解を深めたい人、不安を和らげたい人 | “現場感”を求める人、没入したい人 |
読むならどこまで?怖がりさんへのおすすめスタイル
- 第1章〜第3章までを読む(約20〜30%)
- 登場人物、舞台、取材の背景を理解する
- 結末や重大展開は避ける
- サプライズ性や不穏な連鎖が楽しめなくなる可能性があるため
読むタイミングとしては、
- 【映画前】導入部分だけ読んで心の準備
- 【映画後】結末や裏の真相を読むことで理解が深まる
という使い方がおすすめです。
まとめ
映画『近畿地方のある場所について』は、小説を読んでいても十分楽しめる“体験型ホラー”です。内容を事前に把握しておきたい方、特に怖がりな方には、先に小説を読むことがむしろ良い準備になります。
Web版をすでに読んだ方でも、書籍版には「カラオケの話」などの追加エピソードがあるため、新しい発見があります。
怖いけど気になる——そんなあなたにこそ、小説と映画の“両刀使い”をおすすめします。
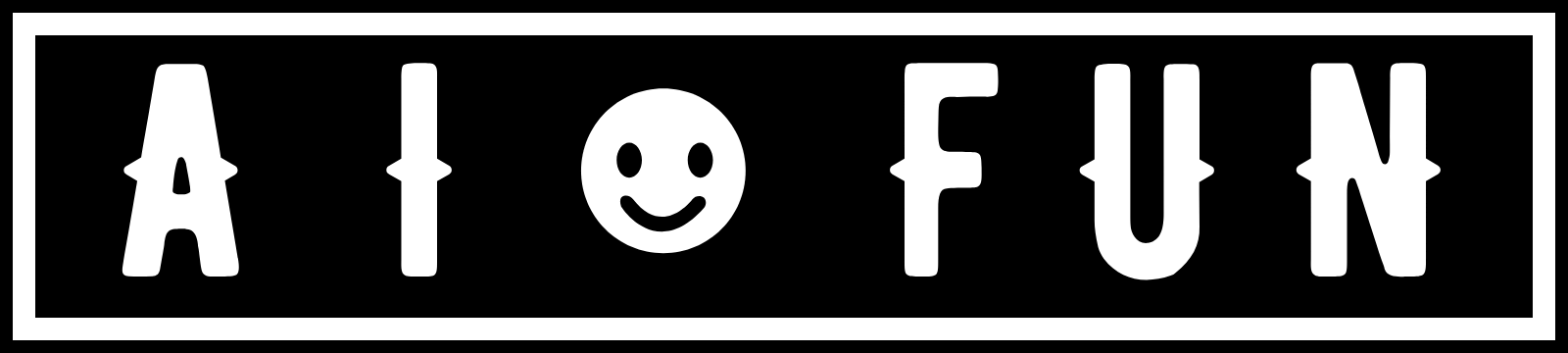
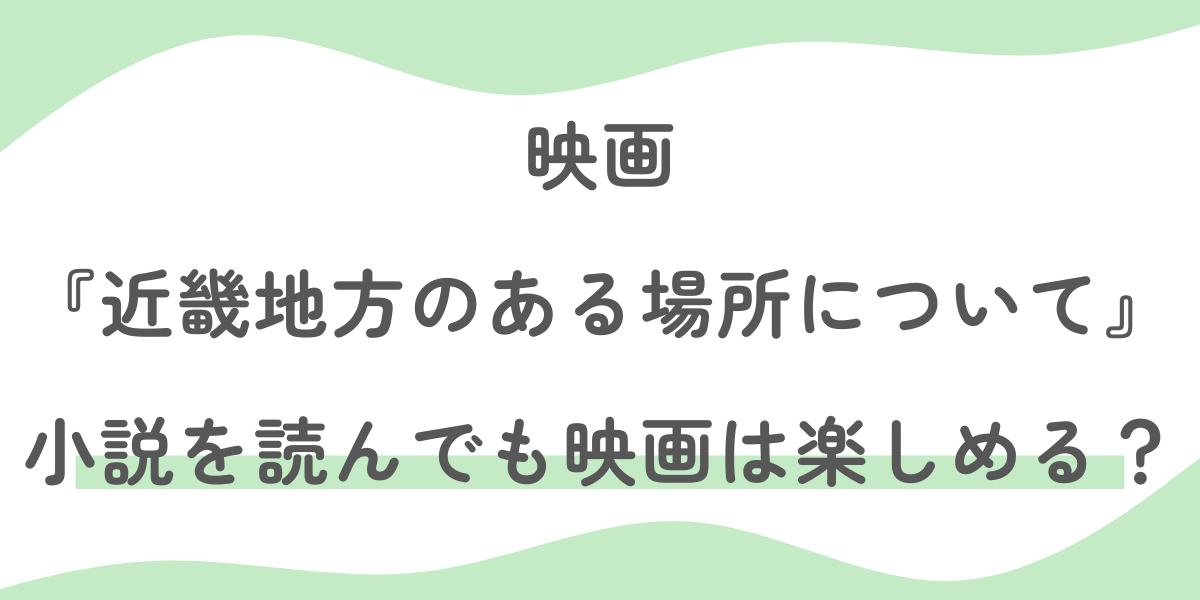
コメント